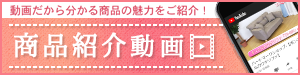�o�b�O
�o�b�O
 ����ɂ���
����ɂ���
 ���}�_�ł�
���}�_�ł�
�{��9��7���͓�\�l�ߋC���u���I�v�i�͂���j�ł��B
�������琔����15���ڍ��ŁA��������u���H�v�ɂȂ�܂�
���̗t�ɔ����I�����ԂƂ����Ӗ��Ŗ��t����ꂽ���I�ł����A�܂��܂��������c���������Ă��܂����
���������M���ǂɂ͏\���Ȓ��ӂ��K�v�ł����A�H���łɂ��C��t���Ȃ�������܂���
���������܂ŐH�ׂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ٓ��͂ƂĂ��S�z�ł�
���ہA�����ɂ��ٓ����̊W���J�����Ƃ��A���ȏL���������Ƃ����o�����������̕��A�ӊO�Ƒ����̂ł͂Ȃ��ł��傤��
������}�_������܂�
����͒�����č�����|�e�g�T���_���炿����ƌ��ȏL���������̂ŁA�R���r�j�ɂ��ٓ����ɑ���܂����E�E�E
��l�Ȃ玩���Ŕ��f���ł��܂����A�S�z�Ȃ̂͂��q�l�ł����
�c�t�����⏬�w���̂��q�l�́A�C�t�����ɐH�ׂĂ��܂��댯���傢�ɍl�����܂�
�����Ŗ{���́A���}�_�����ׂ��A���ٓ������錴���≷�x�A�\�h���@�A�I�X�X���̂����������Љ�����Ǝv���܂�
�܂��́A���̋G�߂����ٓ�������₷�����������������܂�
���ٓ������錴���́A�X�o���u�ہv�ł�
�ۂ��ɐB����Ƃ��ٓ��̋�ނ����߂Ă��܂��u�������v�ƌ�������ɂȂ��Ă��܂��̂ł�
�ۂ��ł��ɐB���₷�����x��35���O���B
�ď�̋C���͂��̉��x�ɋ߂��̂ŁA���ٓ������݂₷���̂ł�
���̂悤�ȏ������ł́A����Ă���Q�`�R���Ԃŕ���n�߂��ƌ����Ă��܂�
�ƌ������Ƃ́E�E�E�E���ɍ�������ٓ������ɂ͍ۂ܂݂��A�Ȃ�Ă��ƂɂȂ肩�˂܂���E�E�l���������ł������낵���ł����
����Ȏ��Ԃ�h�����߂ɁA���ٓ��ɂ͋ۂ�t���Ȃ����ƁA�ۂ𑝂₳�Ȃ����Ƃ�����Ȃ̂ł�
����ł͂�������́A���S�Ȃ��ٓ������|�C���g�����Љ�Ă����܂�
�@ �܂��͂�������Ǝ�����
�����O�ɂ͂�������Ǝ����Ƃ���ł�
���ۂɂ��Ό����g���A�w�̌҂�܂̐�܂ł���������܂��傤
�ŋ߂ł͗��������ۂ�Web��̃��V�s���Q�l�ɂ������������Ǝv���܂��B
���͂��̍s�ׂɂ�������Ɗ댯�����B��Ă���̂ł�
������X�}�[�g�z����^�u���b�gPC�ɕt�����Ă���l�X�ȍ�
�ۂ𗿗��ɍ��������Ȃ����߂ɂ��A�����̑O�ɂ���ʂ����ۃV�[�g�Ő@�����A�G�邽�тɎ������Ƃ������߂��܂�
�A ���ٓ������悭����Ă������芣��������
�ۂ͉Ă̋C�������łȂ��A��������D���ł�
�ł�����A�悭���C��邱�ƂŁA���Ȃ�ۂ̔ɐB��h�����Ƃ��ł���̂ł���
�ł��E�ی��ʂ������̂́A�M���������ċۂ����ł���������
���������ٓ����̑f�ނɂ���Ă͂ł��Ȃ����Ƃ�����̂ŁA�M�Ɏア���ٓ����̏ꍇ�́A�Ƃɂ�����܂ł�������Ɛ܂��傤
�L�b�`���y�[�p�[�ɂ��|��t���Ă��ٓ�����@�������ł��R�ی���������܂���
�B �ł��邾���f��ŐH�ނ�G��Ȃ�
�����炵������Ǝ�������Ƃ��Ă��A�������ɂ��낢��ȕ���G���Ă��܂��ƁA�ǂ����Ă��ۂ���ɕt���Ă��܂��܂�
�܂��A����Ă�����Ȃ��ۂ�����܂��̂ŁA�H�ނ͐����ȍؔ��Ő���t�������Ƃ������߂��܂�
���ɂ�������ڎ�ň���̂ł͂Ȃ��A���b�v�ɕ��ň���܂��傤
���b�v���g���Ɛ����Ƃ��������łȂ��A���т̔M�����ɘa����Ĉ���₷���ł���
�C ���M�͂��������
�Ƃɂ������܂ł�������Ɖ�ʂ���������
���ɒ��܂ʼn��ʂ��������f���Â炢���g����A�n���o�[�O�Ȃǂɂ͗v���ӂł�
�܂��A���Ă����ŗ��Ɋւ��āA���n�����D�݂̕��������Ǝv���̂ł����A���̋G�߂͂�����Ɖ䖝������������Ɖ�ʂ����Ƃ����点�Ȃ��錍�ł��B
���͖Z�����̂őO���̖�ɂ��ٓ��̏�����������A�ӂ��т̎c�蕨�����ٓ��̋�ނɂ����肷�邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B
���̍ۂ��A���A��x���M���邱�Ƃ�����ł�
�D ���ٓ��̋�ނ͗�߂Ă���l�߂�
���т��ނ�M���܂܂��ٓ����ɋl�߂ĊW������ƁA���C���������Ď��x�������Ȃ�܂�
���ɂ��т͗�߂ɂ��̂ŁA�ۂ��D�މ��x�т����������A���̂�������ɂ߁A�ۂ��ɐB���₷����������Ă��܂��̂ł�
���т��ނ͗�܂��Ă������邩�A�������܂ܓ��ꂽ�Ƃ��Ă���߂�܂ŊW�����Ȃ����Ƃ�����ł�
���ɂ���ɊC�ۂ������^�C�~���O���A�܂��������������ƊC�ۂ����݂₷���Ȃ�܂��̂ŁA��߂Ă��犪���܂��傤
�E �����͂�������Ɛ�
�u�ߕ��͐������������������������B
�ϕ��̏ꍇ�A�Ϗ`�͂�������Ɛ��ē�������Ƃł�����x�ɂ݂�\�h�ł��܂�
���Ђ����͂悭�����i���������Ŋ��߂�C�ہA���܂ȂǁA�`�C���\���ɋz�킹���������B
�����ʕ����l�߂�Ƃ��ɂ́A�悭�A���C��������Ɛ�悤�ɂ��܂��傤�B
�ʂ̊�ɓ���Ď����Ă����̂��ǂ����@�ł�
�܂��A�\�[�X�E�h���b�V���O�E�ݖ��E�ӂ肩���Ȃǂ͕ʗe��ɓ���A�H�ׂ钼�O�ɂ����܂��傤
�F �ۗ�܂�R�ۃV�[�g�����p����
���ٓ��̉��x���オ��Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�ۗ�܂�ۗ�o�b�O���g�p���邱�Ƃ������߂��܂�
�܂��ۂ̑��B��h���R�ۃV�[�g�����ʓI�ł�
�������R�𓀉̗Ⓚ�H�i��A�s�̂̏������[���[�𓀂����܂ܓ�����ƁA�ۗ�܂Ɠ������ʂ�����̂ł�����������
�܂��F�l�̒��ɂ́A���ɂ��т�������悤�ɁA��̂����ɂ��Ă������Ń^�C�}�[�ŃZ�b�g����Ă�����������ł����
�ł��A�܂��܂���Ԃł����\�C�����������������Ă��܂��B
���R�������u����A���܂蕅���̂ł�
���ъ�̒��ɐ��Ƃ��Ă���ꂽ��ԂŒ����ԕ��u���Ă����ƁA�����ꂽ�����̒��łǂ�ǂ�ƍۂ��ɐB���邱�Ƃ�����܂�
������āu�䂪�Ƃ̂��т͊�Ȃ��v�Ɗ�@�����o�����F�l�A�����S�������B��͂���܂���
�����ł����ъ���̉��x���オ��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�^�C�}�[���Z�b�g����̂͐Q�钼�O�ɂ��܂�
����ɁA���ъ�ɂ͐��ƈꏏ�ɕX������������܂��B
�X�̂������Ő��̉��x�㏸���}�����A�ۂ��ɐB���ɂ����Ȃ��܂���
���ƕX�����킹�ĕ��i�̐����ʂɂ��Ă����A��������������i�ƕς��܂���
����ł́A���ٓ��̂������͉����ǂ��ł��傤��
�������߂Ȃ̂��A���I�A�����A�~�����A�킳�тȂ����g���������ł��B
�����̐H�ނ��R�ۍ�p������̂őS�̓I�Ȗ��t���Ɏg���̂����z�I�ł�
�܂��A�u�~�����͎E�ی��ʂ���������A����Ă���������v�v�ƌ����b���悭���ɂ��܂����A�~������1�����ɒu�������ł͎��ӂ��E�ۂ���邾���Ȃ̂ŁA���ٓ��S�̂̎E�ی��ʂ͂��܂���ʂ����҂ł��܂���
�ׂ������Ă܂�ׂ�Ȃ��U�炵����A�������肵�����������ʓI�ł�
���ɁA�ď�ł����݂ɂ����������́A����҂�A�g�����A�s�̗̂Ⓚ�H�i�ł�
����҂���g��������̐��������Ȃ��Ȃ��Ă��邽�߁A�ď�̂��ٓ��ɂ҂�����Ȃ̂ł���
����҂�́A�S�{�E�����łȂ��A�����R���A�l�Q�A�s�[�}���Ȃǂł����܂��̂ŁA����������A�����W������ΖO���܂���B
�g�������A���g���A�����`�J�c�A�ƂA���̓��g���ȂNj�ނ�ς��č���Ă݂ĉ�����
���ɓ��g���ɂ͐��I���g���A���R�ۃA�b�v�ł��܂�
�������A�����g�����ł��R���b�P�́A���݂₷�����Ⴊ�����𑽂��g�p���Ă���̂ŁA���̎����͔������ق��������ł�
�������ł���
��Ȃ��Ƒ��A�����Ă����g�̊y���������`�^�C���̂��߂Ɏ����Ă݂ĉ������B
�Ƃ������ƂŁA�{���͈��S�ȃ����`�^�C���Ɉ���A�o�b�O�����Љ�܂�
�yOkato�^�I�J�g�[�zBigBee �r�b�O�r�[ �������Ɏ������� �ۗ�BOX�^ �N�[���[�����`�o�b�O
������͌��Ɋ|�������Ɏ�������ƁA���퐶���Ɏg����֗��ȃN�[���[�����`�o�b�O�ł�
BOX�^�Ȃ̂��J�������傫���J���A���̏o�����ꂪ���N���N�ł�

�_�u���t�@�X�i�[���O�ʂ̃|�P�b�g�Ȃǎg���₷���͔��Q

�����ł������₷���T�C�Y�ł��e�ʂ͑傫���A500ml�̃y�b�g�{�g���Ȃ�6�{���[�ł��܂�

�J���[���R�b�g���A�C�{���[�E�I���[�u�O���[���E�n�j�[�x�[�W���E�I�[�V�����l�C�r�[��4�F
���D�݂ł��I�ђ����܂��B



�ʋ�ʊw�͂������A���W���[�₨�������ɂ��g�����N�[���[�����`�o�b�O�B
�܂����炭���������ȍ��N�̎c���ɁA�傢�ɖ𗧂��Ă��ꂻ���ł����
 ����ɂ���
����ɂ���
�~�Y�^�j�ł��B
���悢�����N��7��1�����A���W�܂̗L�������n�܂�܂�
���X�[�p�[�Ȃǂł͂��łɎ��{���Ă���Ƃ���������ł���ˁB
�v���X�`�b�N�́A�`�����₷����Ɍy���ď�v�łƂĂ��֗��ȑf�ނł�
�ł����̈���A�̂Ă��Ă��܂�����A���܂Ōo���Ă��y�Ɋ҂邱�Ƃ͂Ȃ��A�S�~�ƂȂ��Ċ��������Ă��܂��܂�
�܂��C�Ɏ̂Ă�ꂽ�v���X�`�b�N���i���n���邱�ƂȂ����V���A�Ō�ɂ͊C�݂ɑł��グ���A�C�݉����̌����ɂȂ��Ă��܂��̂ł�
���̑��ɂ��A���������n�����g���Ȃljۑ�͂�������܂�
�������͒n���̂��߂ɁA�����Ď������̍K���Ȗ����̂��߂ɁA������v���X�`�b�N�̉ߏ�Ȏg�p��}�����A�������p���Ă����K�v������܂��B
���W�܂̗L�����͂��̂悤�Ȋ����̈���Ȃ̂ł�
���i�A���C�Ȃ�������Ă��郌�W�܂�L�������邱�ƂŁA���ꂪ�{���ɕK�v�����l���A���C�t�X�^�C�������������������Ƃ��邱�Ƃ�ړI�Ƀ��W�܂̗L�������n�܂�̂ł�
�����ă��W�܂̗L�����ɔ����A�K�v�s���Ȃ̂��G�R�o�b�O�ł����
�����ŁA�{���̓G�R�o�b�O���L�܂����o�܂ɂ��Ă��b�����܂��B
���̐́A�܂����{�Ƀ��W�܂ȂǂƂ����������݂��Ȃ�����1950�N�㍠�A���{�ł͔�����������Ƃ��ɂ́u�������J�S�v�����Q����̂���ʓI�ȃX�^�C���ł���
�[���߂��ɂȂ�ƁA�J�̔��S������⋛������ɂ͂����ۂ�����g�ɂ܂Ƃ��A�������J�S��r�ɂ�������w�̎p�����������܂����B
�X���ɂ͖�⋛�����̂܂ܕ��ׂ��Ă��āA���������͂��X�ŐV�����Ȃǂɕ��ł��炢�A�J�S�ɓ���Ď����A�������܂����B
�܂��A���ł͐M�����Ȃ���������܂��A�����͓���������ɓ�������Ĕ����ɍs���̂�������O�������̂ł���
������Ƌ����ł����
�܂肱�̎���́A�v���X�`�b�N�̃S�~�͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ������Ƃ������Ƃł�
���̌�A1970�N��ɓ��荂�x�o�ϐ������ɓ˓�����ƁA�l�X�̔������́A����܂ł̔��S���⋛���̂悤�ȏ����Ƃōw������X�^�C������A��^�X�[�p�[�Ȃǂ̗ʔ̓X�ł܂Ƃ߂čw������X�^�C���ւƈڂ�ς���Ă����܂���
���̕ω��ɔ����A����܂ł��������J�S����A��v�ň����ȃ|���G�`�������̃��W�܂��}���ɕ��y�����̂ł�
����Ȗ��A1973�N�ɗ��j�Ɏc��I�C���V���b�N���N���܂���
�����̃g�C���b�g�y�[�p�[�̑��D��̗l�q�́A�挎�N�����V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ���f�}�̉e���ŃX�[�p�[��A�h���b�O�X�g�A�ɍs������l�X�̎p�ɒʂ�����̂�����܂������
�I�C���V���b�N���u�P�Ȃ�̂̏o�����v�Ƃ͎v���Ȃ��Ȃ�܂���
���v���A���̂Ƃ��ɋN�����Ζ������̃��_����������������҉^����A����������S�~����Ȃǂ��A�������G�R�o�b�O���i��A���W�܂̍ė��p���i�Ȃǂ̌[�������̍����ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂�
������1990�N��ɓ��������A�h�C�c�ŕ��y���Ă����z���G�R�o�b�O�����{�ŏЉ��܂���
�����́A�܂��܂��G�R�ɂ��Ă̈ӎ��͔����������{�B
�������A����ƂƂ�����������C�m�����A�������ʃK�X�ɂ��n�����g���Ȃǒn�����x���ł̊���肪�[�������A���X�ɃG�R�ւ̊S�����܂��Ă��܂����B
���̂悤�ȗ���̒��ŁA�ߔN�ł́A�X�[�p�[�ȂǗʔ̓X���G�R�o�b�O�̔̔����J�n�A���W�܂̎��ގ҂Ƀ|�C���g���Ҍ����銄���T�[�r�X�ȂǁA���W�܍팸�^�����W�J����A�G�R�o�b�O�͕��y���Ă����̂ł�
�������ŋߍ��́A�������ȃf�U�C����F�E�T�C�Y�̃G�R�o�b�O�𐔑����������邱�Ƃ��A�����Ȃ�܂������
����ł́A���{�ɃG�R�o�b�O�̏K�����L�߂�v���̂ЂƂƂȂ����h�C�c�̃G�R�o�b�O�Ƃ͂ǂ�ȕ��Ȃ̂ł��傤��
�h�C�c�͊���i���Ƃ��Ēm���邾�������āA�G�R�o�b�O������1970�N���납��n�܂����ƌ����Ă��܂�
���������h�C�c�ł́A�������Ŕ��������������ċA�邽�߂̑܂��x������K���͂Ȃ��A�������Ƃ��Ă��L���Ŏx���Ƃ������X���������߁A�G�R�o�b�O�͓�����O�̂悤�Ɏg���Ă��܂���
�h�C�c�ł̃G�R�o�b�O�̌Ăѕ����u�e���[�e�v�ƌ����A������Ƃ������ꕨ�E��y�ȑ܂Ƃ����Ӗ��Ȃ̂������ł�
�h�C�c�ł̓e���[�e�̎g�p�����������Ƃ�����A1�`3���[���O���Ŏ�ɓ��镨���قƂ�ǂł�
�X�[�p�[�}�[�P�b�g�A���X�A�h���b�O�X�g�A�A���X�g�������ƂȂǂł��I���W�i���̃e���[�e������Ă��āA���L���ȃf�U�C���̃e���[�e�����������݂��Ă��܂��B
�e���[�e�̓h�C�c�̃G�R�ȕ������ے����镨�ł����邱�Ƃ���A�����n�̊G�����v�����g����Ă��镨������A���s�Ńh�C�c��K�ꂽ�ۂɁA���y�Y�⎩�g�̃R���N�V�����Ƃ��Ĕ����ċA��l�����������ł�
���W�܂��L�������鍡��̓��{�ł��A�h�C�c�Ɠ��l�ɃG�R�̕����Ƃ��č���G�R�o�b�O���ǂ�ǂW���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤��
�����Ŗ{���͂Ƃ��Ă��g���₷���A�������X�^�C���b�V���ȃG�R�o�b�O�����Љ�܂��B
�yShupatto�^�V���p�b�g�z�}�[�i �R���p�N�g�o�b�O Drop �t�����[ S460BO
������̓X�^�C���b�V���ȉƒ�p�i�ł��Ȃ����u������Ѓ}�[�i�v����Ă���R���p�N�g�ȃG�R�o�b�O�ł�
�����u�V���p�b�g�v�Ƃ����l�[�~���O�̗R������������ɂȂ�܂���
����͂����ݕ��̃C���[�W
�g��Ȃ��Ƃ��ɃR���p�N�g�ɂ����߂�G�R�o�b�O�͂�������܂����A������̃o�b�O����u�ł����߂Ă��܂��̂ł���
�����ݕ��͂�����B

�l�[�~���O�̒ʂ�A���[�������ăV���p�b�ƈ�������ƈ�C�ɑя��ɂȂ�A���Ƃ͐܂肽���ނ���
�����킸��4cm�̃t���b�g�Ȍ`���ɂ܂Ƃ܂�܂�

�܂肽�����Ƃ��t���Ă���S���łƂ߂Ă������A�ʋo�b�O�̒��ł�������܂���

�����āA���̃o�b�O�̂����ЂƂ̃|�C���g�͓����I�Ȍ`��

�܌������R�ɂڂ܂�u������ �v�`�Ȃ̂ŁA����I�ɂ����Ă���Ƃ��ɁA���g�������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
�v�`�Ȃ̂ŁA����I�ɂ����Ă���Ƃ��ɁA���g�������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
����ɂ����̒ʂ��c���Ȃ̂ŁA�X�y�[�X����炸�A���d���A��ȂǁA�����������Ă���d�Ԃ�o�X�ɏ��ہA�����d�Ԃł��ז��ɂȂ�ɂ����̂����͂ł�
�܂����̑܌��A�����グ��Ƃ��͂ڂ܂�̂ł����A��������ۂɂ͂��Ȃ�L����܂��̂ŁA�P�[�L���Ȃǂ̑傫�ȕ����ȒP�ɓ���܂���

�e�ʂ�16L�A�ωd5kg�Ƃ����Ղ����܂����A���ʂ̑܂ł͂��܂�����Ȃ��l�M��o�Q�b�g�Ȃ����ׂ��������肵�ē�����܂�

�o���G�[�V�������L�x�Ȃ̂ŁA���D���ȃJ���[�╿�����I�ђ����܂�


�y���Ă����炸�A�����������G�R�o�b�O�u�V���p�b�g�v�B
�Ƃ��Ă��������ł�����A���������p�Ƃ��Ă����łȂ��A���o�����̍ۂ��T�u�o�b�O�Ƃ��Ă��g�p�ł��܂����


�����Ƃ����Ƃ��ɖ𗧂��܂�����A�����J�o���̒��ɓ���Ă����ƕ֗��ł���
�yShupatto�^�V���p�b�g�z�}�[�i �R���p�N�g�o�b�O Drop �t�����[ S460BO
 ����ɂ���
����ɂ���
�~�Y�^�j�ł��B
�H�������Ɛ[�܂��ĎQ��܂���
�g�t�ŐԂ≩�F�ɐF�Â����i�F�����Ă���ƁA����̌�����Y��A�S��������܂����
���̋G�߂̎��̊y���݂́A�e�n�̍g�t�X�|�b�g������A���̑f���炵�����J�����Ɏ��߂邱��
���̂Ƃ��ɁA�C�ɂȂ�̂��J�����̉^�ѕ��ł�
���̂܂��������ƁA�����炱������J�������Ԃ��ď���t���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z
���ƌ����āA�J�o���ɓ���Ă��܂��ƁA�B�肽���Ƃ��ɏo�����ꂪ��ςł�
����ȔY�݁A�F�l�������Ă���������̂ł͂Ȃ��ł��傤��
�����Ŗ{���́A�ʐ^���B��Ȃ�������Ƃ��ɖ𗧂J�����o�b�O�����Љ�܂�
�yELECOM�^�G���R���z off toco �I�t�g�R ���t�J�����p �o�b�N�p�b�N
������́A�J�����������^�ԍۂɂƂĂ��֗��ȃo�b�N�p�b�N�ł�
�����́A�o�b�O�������ɂ���J������p�̎��[��
���̎��[��������y�ɃJ��������Y�����o���܂�

���̗l�ɁA�o�b�O�����Ɋ|�����܂܃J�����̏o�����ꂪ�ł����̂ŁA�Ƃ��Ă��֗�
���������[���ɂ́A�����Ɏ��o���\���n���h�����̃_�u���t�@�X�i�[�ƁA�����o�����X�}�[�g�ɊJ�ł����}�O�l�b�g�t���b�v���̗p���Ă��܂��B
����Ȃ�A�����Y�̕t���ւ������N�ɂł������ł����

����ɁA���[���̒��ɂ����E�\�ȃJ�����̃C���i�[�P�[�X�������Ă����A�����̃t�@�X�i�[�Ńo�b�O�������㉺�ɕ��������̂ł�
���̎��[���ŁA�J��������Y�����t�����Ƃ�h���܂���
�t�@�X�i�[��������ăC���i�[�P�[�X���O���A�o�b�O�����ЂƂ��Ȃ�A�傫�߂̉ו��ł�����邱�Ƃ��ł��܂���

�C���i�[�P�[�X�ɂ́A���߉\�Ȏd������t���Ă����J��������Y�̑傫���ɍ��킹�ĕς������̂��|�C���g
�������A���̃o�b�N�p�b�N�̖��͂͂��ꂾ���ł͂���܂���
���̑��̖��͂��ǂ�ǂЉ�Ă����܂���
�@ �֗���3�̃A�E�^�[�|�P�b�g
�V�����_�[�x���g�����ɁAIC�J�[�h�Ȃǂ̎��[�ɕ֗����~�j�|�P�b�g�A�O�ʂɂ͑傫��L���^�ɊJ���ł��āA�蒠�Ȃǂ̏��������o���₷����^�|�P�b�g�t���B
����ɁA�w���ɓ�����ʂɂ̓o�b�O�����낳���ɃX�}�[�g�t�H���Ȃǂ����[�\���w�ʃ|�P�b�g���t���Ă��܂�
�ǂ̃|�P�b�g���t�@�X�i�[�t���ŁA�ړ����Ɏ��[������яo���S�z������܂���

�A �p�\�R�����[�����S
�\�ʂɂ͝������H���{���A�C���i�[�w�ʂɂ�14�C���`�܂ł̃p�\�R�������[�ł�����p�|�P�b�g���B
��ȃp�\�R���̎����^�т����S�ł�

�B �J�����ȊO�̏������֗��Ɏ��[
�㕔�̎��[�X�y�[�X�ɂ́A���z��y�b�g�{�g���Ȃǂ����[�ł��鑼�A�����̎��[�ɕ֗������b�V���|�P�b�g�ƃt�@�X�i�[�|�P�b�g�t��
�C ���s�ɂ��֗��ȃL�����[�x���g
�w�ʂɂ́A�L�����[�o�[�Œ�ł���L�����[�x���g��z�u���Ă���̂ŁA���s���̈ړ������N���N�ł�

�D ��Ƃ��Ă������₷���_�u���n���h��
�莝���̍ۂɈ��肵�Ď����Ƃ��ł����_�u���n���h�����̗p���Ă��܂�

�J���[�́A�����܂ł��Љ�Ă����u���b�N�̑��A�l�C�r�[�ƃO���[��3�J���[
�ǂ̃J���[���C���i�[�ɂ͖��邢�J���[���g�p���A���[�����������₷���Ȃ��Ă��܂�


�J�����p�����łȂ��A���i�g���ɂ��֗��ȃo�b�N�p�b�N
�F�l�̃��C�t�X�^�C���ɂ��Ђ��𗧂ĉ�����
 ����ɂ���
����ɂ���
 ���}�_�ł�
���}�_�ł�
���̃u���O�ł́A���낢��Ȏ�ނ��usasicco�i�T�V�R�j�v�̃o�b�O�����Љ�Ă��܂���
����A�܂��܂��I�X�X�����������̂ł��Љ�܂��ˁB
�usasicco�v�Ƃ��u�O�͖ؖȁv�������ɂ��āA�u�h���q�D��v�Ƃ����Z�p�ō��ꂽ�o�b�O�̃u�����h�ł��B
�ysasicco�i�T�V�R�j�z
https://www.heartmark-shop.com/category/F001/
�usasicco�v�̃o�b�O�͎�ނ�������ɁA��v�Ŏg�����肪�ǂ��̂ŁA�l�X�ȃV�[���Ŋ��܂�
���}�_���g�[�g�o�b�O�Ȃǂ��g���Ă��܂����A���\�G�Ȉ��������Ă��S���j��Ȃ��̂ł���
�u�h���q�D��v���ϋv���A�ωΐ��A�ۉ����A�z�����ɗD��A���G����ǂ��̂ŁA�u���̗ǂ��ȐD���v�Ƃ��č]�ˎ��ォ��p����Ă��܂��B
�܂��A�O�͖ؖȂ��_�����̐��n�ɂ��g�p����Ă���̂ŁA���̏�v�����M���܂���


����́A���̒����烊���b�N�����Љ�܂�
sasicco�@�����b�N�@���h�h���q

�����̒ʂ�A�ƂĂ��V���v���Ŏg���₷�������b�N�T�b�N�ł�
�����Ղ�����̂ŁA�ʋ�ʊw�����łȂ��A�n�C�L���O��y�߂̓o�R�Ȃǂł����܂�
�܂����̃����b�N���w���Ƀt�B�b�g����`��Ȃ̂ŁA�ו��������Ղ�l�ߍ���ŏd�����Ȃ��Ă��A�g�̂ɕ��S��������ɂ����̂ł���

�O���ɂ��傫�ȃ|�P�b�g���t���Ă���̂ŃX�}�z��蒠�A�n���J�`�Ȃ��p�ɂɎg�p���镨�����Ă����A�o�����ꂪ���N���N

�����āA���̃o�b�O��Ԃ̖��͂͂�͂���v�Ȃ���
���イ���イ�̖����d�Ԃŝ��܂�Ă��A�p���p���ɂȂ邭�炢��������̉ו������Ă��A�����Ƀ|���ƕ���o���Ă��A�قꂽ��C�ꂽ�肵�ɂ����̂ł���


�J���[�́A���h�h���q�ƍ���2�F�B
�ǂ���̐F���V���v���Ȃ̂ŁA�Ⴂ�����炲����҂܂ŕ��L���N��w�̕��X�ɂ��g�������܂�


���]�Ԃ�o�C�N�ł��g����sasicco�̃����b�N�B
�F�l�̂��o�����A�C�e���Ɏ�����Ă݂Ă͂������ł���
sasicco�@�����b�N�@���h�h���q