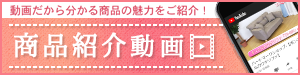�T�j�^���[�`�F�X�g
�T�j�^���[�`�F�X�g
 ����ɂ���
����ɂ���
�~�Y�^�j�ł��B
�}�G�_�X������u����w�������g�C���b�g�y�[�p�[�X�g�b�J�[�̎g���S�n�͂ǂ� �u���O�ɏ����Ă�����
�u���O�ɏ����Ă����� �v�ƌ����E�E�E
�v�ƌ����E�E�E
�ǂ��@��Ȃ̂��g�C���b�g�y�[�p�[�ɂ��Ē��ׂĂ݂悤�Ǝv���܂���
���i�A�g�C���b�g�y�[�p�[�ɂ��Ă��܂�l���邱�Ƃ͂Ȃ��ł����
�Ƃ������ƂŁA�܂����g�C���b�g�y�[�p�[�̗��j����
���␢�E���̑����̍��̃g�C���Ŏg�p����Ă���g�C���b�g�y�[�p�[�ł����A�a�������͌����ă��W���[�ȕ��ł͂Ȃ������悤�ŁE�E�E
�������j�̒��ŗl�X�ȉߒ����o�āA�悤�₭���݂̂悤�ɓ�����O�Ɏg���鑶�݂ɂȂ��������ł���
�p�𑫂����Ƃ��ɏ���������f�ނƂ��āA�ŏ��Ɏ����g����悤�ɂȂ����̂́A1300�N�O�̒����������ƌ����Ă��܂�
�ƌ����Ă������g���Ă����̂̓��[����ł͂Ȃ��u���莆�v�B
�����������g���͍̂����g���̐l�Ɍ����Ă����A���߂ĕ����ɓo�ꂵ�����p�҂́A6���I�̒����̍c��⓯����̕x�T�w�������Ƃ������Ƃł�
���̌�A�g�C���Ŏ����g���K���͏��X�ɒ����S�y�ɕ��y���Ă����A14���I�ɂ͟��]�Ȃ������N��1,000���̃g�C���p�́u���莆�v�����Y�����܂łɂȂ�܂���
�Ƃ��낪�A���ꂾ�������ŕ��y�����g�C���p�́u���莆�v�ł����A���̍��ł͂Ȃ��Ȃ�������܂���ł���
����ǂ��납8���I�ɒ�����K�ꂽ���X�����̗��l�́A�u�����̐l�X�͗p�𑫂������ƁA�����̑̂𐅂Ő�킸�A���̕��������Ő@����邾���ōς܂���B�ނ�͂��܂萴�����ɂ������Ȃ��悤���v�ƋL���Ă���قǂł���
����ł͐��E�̐l�X�́A�p�𑫂������ƁA���������ǂ��������Ă����̂ł��傤��
���̕��@�͍���n��ɂ���ėl�X�������悤�ł��B
�Ⴆ�A�Ƃ��鍑�̗T���Ȑl�X�͗p�𑫂������ƁA����[�X�A�r�т��g���Ăʂ����Ă�������ŁA�n�����l�X����ŗp�𑫂��A���̐��ő̂�����Ƃ������������ł��B
���邢�́A�ڂ낫���̂���Ȃ����A�t���ς⊱�����A�⍻�A�͂��܂��C�����̔�A�L�k�A�V�_�A���ȂǁA�育��ł����̂�����Ȃ����ŏ������Ă����������Ă��������ł�
���{�ł́A�Â��͒�����Ő@�����A�A���̗t��C���Ȃǂ��g�p���Ă��܂������A�ޗǎ���ɓ����Ă���ׂ��̖_�ł����u���イ���v�Ƃ����̂ւ����g����悤�ɂȂ�܂����B
���̌�́A���Ő@���̂���ʓI�ȏ������@�ɂȂ����ƌ������Ƃł�
���ɂ����낢����@�͂���悤�ł����A����ȏ�͂����Ċ��������Ē����܂���
���Ăŗp�𑫂����㏈���Ɏ����g����悤�ɂȂ����̂́A������肩�Ȃ�x��Ă̂��Ƃł����B
1857�N�A�A�����J�̎��ƉƁA�W���Z�t�E�K�G�e�B�́A���̍��l�X���p�𑫂����㏈���ɐV������Î����g�p���Ă���̂����āA�����Ǝg���S�n�̗ǂ��g�C����p�̃y�[�p�[�i�ꖇ�ꖇ�̃V�[�g�^�C�v�j�̍H�Ɛ��Y�Ɏ�肩����A�s�̂Ɍ����ē����͂��߂܂���
�Ƃ��낪�A�l�X�́u�V�����ŏ\���v�Ɗ����Ă����炵���A�킴�킴�g�C����p�̃y�[�p�[���l�͏��Ȃ��A�قƂ�Ǖ��y���Ȃ������悤�ł�
���ۂɍ��g���Ă���悤�ȁA���[����Ő^�Ɍ����J���Ă���^�C�v����������͂��߂��̂�1877�N����1879�N���B
������C�M���X�ŏ��i������܂���
�ƌ����Ă��A���̃g�C���b�g�y�[�p�[�������Ɉ�ʉ������킯�ł͂���܂���
�L���g����悤�ɂȂ������������́A1880�N��Ƀ��[���b�p�A�A�����J�̑�s�s�ł̌��������������ł����B
���̍��A���X�Ɉ�ʉƒ�ɃV�����[��g�C���������悤�ɂȂ�A�����ŐV���̕֊�u��̐��^����t�֊�v�A���Ō����m���g�C���������̔������悤�ɂȂ�܂���
�����u��̐��^����t�֊�v����ʉƒ�ɍL�܂邱�Ƃɂ��A�g���₷���g�C���b�g�y�[�p�[�͈�ʂ̐l�Ɏ������A���ł͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂȂ����̂ł�
���{�Ńg�C���b�g�y�[�p�[���ŏ��Ɏg����悤�ɂȂ����̂́A�����ېV��̃z�e����m��
�����͂킴�킴�C�O����A�����Ă��������ł�
����A��ʉƒ�ł͖����̒������璷���ԁA�Î��������̂��莆�ƁA�p���v������ꂽ���Ԏ��i���Ƃ����j���g���Ă��܂���
���̌�A�������H�����{�i���������a30�N�O�ォ���u���ݎ�莮�v����u���v�ցA�u�a���֊�v����u�m���֊�v�ւƕω����܂����B
����ƂƂ������莆���[�J�[���g�C���b�g�y�[�p�[�����n���A��ʉƒ�ɂ��L�����Ă������̂ł�
�����������̎��͍��ƈႢ�z�����������n���ɂ����A�ł��������߁A��ł���Ŏg���Ă��������ł���
���i���C�Ȃ��g���Ă���g�C���b�g�y�[�p�[�ɂ��A����ȗl�X�ȗ��j���������̂ł���
����ł͂�������̓g�C���b�g�y�[�p�[�ɂ��Ă̓��m�������Љ�܂���
�@ �g�C���b�g�y�[�p�[�ƃe�B�b�V���y�[�p�[�̈Ⴂ
�g�C���b�g�y�[�p�[�͐��ɂق���₷���̂������ł�
����A�e�B�b�V���y�[�p�[�͏�v�ŁA�����܂�ł��ق���ɂ����ł��Ă��܂�
�ǂ�����A�p���v�̗n�����犣���܂ł̍H���͂قړ����B
�Ⴄ�͎̂d�グ���@�ł�
�@�ۂƑ@�ۂ�����������̂��f���v�����g���Ă���g�C���b�g�y�[�p�[�ƈႢ�A�e�B�b�V���y�[�p�[�������i�������͑����܁j�����Ĕj��ɂ������Ă��܂�
�e�B�b�V���y�[�p�[�͏�v�ŗǂ��̂ł����A���̕��g�C���ɗ����Ƌl�܂錴���ɂȂ�܂�����A�p�r�ɉ����Đ������g�����Ƃ���ł����
�A �g�C���b�g�y�[�p�[�̕��̔閧
�g�C���b�g�y�[�p�[�̕���JIS�K�i�ł�114�~�����ł�
�ł�������ĂȂ����r���[�Ȑ������Ǝv���܂���
����́A���{�Ƀg�C���b�g�y�[�p�[���Ȃ�����A�A�����J����@�B��A�����Đ��Y���n�߂����Ƃɐ[����������Ă��܂�
�A�����J�ł͕��̒����𑪂�Ƃ��A����u�C���`�v�ƌ����P�ʂ��g�p���܂��B
�ł�����A���������H�@�����R�C���`�T�C�Y�d�l�B
�����̉��H�@�łł����g�C���b�g�y�[�p�[�̕���4.5�C���`�������̂ł����A������~���P�ʂɊ��Z�����114�~���������̂ł��B
�Ȍ�A���{�ł�114�~������JIS�K�i�ƂȂ�܂���
�B �g�C���b�g�y�[�p�[�̃~�V���ڕ��̗��j
�g�C���b�g�y�[�p�[�ɂ́A�~�V���ڂ������Ă��܂���ˁB
�~�V���ړ��m�̊Ԋu�͂ǂ̂��炢���Ǝv���܂����H
���X�g�C���b�g�y�[�p�[�́A�����`�̎����Ȃ��������Ƃ��čl�����Ă��܂���
�����牡����11.4�Z���`�Ȃ̂ŁA�~�V���ڂ̊Ԋu�̒�����11.4�Z���`�Ȃ̂ł��B
�����͓��{�ł��A11.4�~11.4�Z���`�Œ蒅���Ă����̂ł����A�~�V���ڂ�����@�B�̎����Ɍ��炵22.8�Z���`�ɉ��ǂ��܂���
�Ȃ��������ǂ����̂��ƌ����ƁE�E�E
�~�V���ڂ̊Ԋu���Z���Ƃ������Ƃ́A�~�V���ڂ̐��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�l��1��Ɏg�p���鎆�̒������A�����̃~�V���ڂł�����2�ڕ����炢�B
�����Ȃ�ƁA�@���Ƃ��Ɏ��̐^�Ƀ~�V���ڂ�����m���������Ȃ�܂��B
�~�V���ڂ͔j��₷���肪����Ă��܂����Ƃ������������̂ŁA�^�̃~�V���ڂ��Ȃ������߂ɁA1�ڕ��̒�����2�{�ɂ����̂ł�
���݂��A�~�V���ڂ�JIS�K�i�͂���܂���B
���ł̓��[�J�[�̋@�B�����l�����i�݊Ԋu�͗l�X�ł����A23�Z���`�O��ɐݒ�����Ă��郁�[�J�[�������悤�ł�
�C �g�C���b�g�y�[�p�[�̎O�p�܂�
�z�e���̃g�C���Ȃǂł悭�g�C���b�g�y�[�p�[���O�p�ɐ܂��Ă����̂��������܂���
����͂��Ƃ��Ə��h�m�̊Ԃł���Ă����K���ŁA�u�t�@�C���[�z�[���h�v�ƌĂ�Ă��܂����B
�ǂ̂悤�ȏ��ł����Ă��o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����h�m���A������������悤�ɂƂ����S�\�������n�܂��������ł��B
�������ʓI�ɍL�߂��̂͒鍑�z�e���̐��|���ł�
�����̐��|���́A�|�����I�������ڈ�Ƀg�C���b�g�y�[�p�[���t�@�C���[�t�H�[���h�ɂ����ƌ����Ă���̂ł�
���݂ł��t�@�C���[�t�H�[���h���}�i�[�ƍl���āA�g�C���b�g�y�[�p�[���O�p�܂�ɂ���l�����܂����A�g�p�ς݂̎�Ő܂邽�߁A�u�������ă}�i�[�ᔽ�v�u�l���G�����Ǝv���ƋC���������v�u�s�q���v�Ɗ�����������������ł�
�D �g�C���b�g�y�[�p�[�̕\��
�g�p���Ă���g�C���b�g�y�[�p�[���悭����ƁA�ʉ��������܂���ˁB
������G���{�X���H�ƌ����܂�
���̃G���{�X���H���{�����Ƃɂ�����������炩���Ȃ�A�@���S�n���ǂ��Ȃ��̂ł���
���ׂ�Β��ׂ�قǁA�g�C���b�g�y�[�p�[���Ă������낢�ł����
�����Ŗ{���͖`���ł����`�������悤�ɁA�g�C���b�g�y�[�p�[�̎��[�ɖ𗧂O�b�Y�����Љ�܂�
�yOKATO �^�I�J�g�[�z �g�C���b�g�y�[�p�[ �X�g�b�J�[ 4���[�����[
������́A������\���̃g�C���b�g�y�[�p�[������������[���邱�Ƃ��ł���A�g�C���b�g�y�[�p�[�X�g�b�J�[�ł�
�X�����ȃf�U�C���Ȃ̂ŁA�����g�C�����̋�Ԃł��u���X�y�[�X�ɍ���܂���
�X�g�b�J�[�̉����Ƀg�C���b�g�y�[�p�[������o���\���ɂȂ��Ă���̂ŁA�Ў�ŊȒP�Ɏ��o���܂�
�܂��A��[�͏�̃t�^���J���ăT�b�Ɠ���邾��
�ȒP�Ƀg�C���b�g�y�[�p�[�̕�[���ł���̂��������|�C���g�ł����
�T�C�h�̓��b�V��������A�g�C���b�g�y�[�p�[�̎c�ʂ��ЂƖڂŊm�F�ł��܂�

�V���v���ȃf�U�C���Ȃ̂łǂ�ȃC���e���A�̃g�C���ɂ��悭����݂܂���
�J���[���A�C�{���[�ƃ~���g�O���[����2�F�A�T�C�Y��4���[�����[��5���[�����[��2�T�C�Y�B
���D�݂�p�r�ɍ��킹�Ă��I�ђ����܂�




1877�N���g�C���b�g�y�[�p�[�����܂ꂽ�Ƃ��ɁA����Ȃɕ֗��ȃX�g�b�J�[������A�����Ƒ����g�C���b�g�y�[�p�[�������L��������������Ȃ��ł���
�ƂĂ��֗��ȃg�C���b�g�y�[�p�[�X�g�b�J�[�A�F�l�̂���ɂ��������ł���
����ɂ���
���[�L���O�}�U�[�̃^�J�n�V�ł��B
�F�l�̂�����ł́A����@�͂ǂ��ɒu���Ă���܂���?
�E�ߎ��ɒu����Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤��
�E�ߎ��Ȃ�E�����m���������ɐ���@�ɓ�����܂����A�����ƕ֗��ł�
�����A�E�ߎ��͈ӊO�ɋ����ł����
�����āA�����������Ȃ��Ă��܂��܂�
���ʗp��͂������A�^�I���A�\���̐Ό��A�����܁A�h���C���[�ȂǁB
�����ɉ����āA����p�̐�܂�_��܂܂ʼn��������A���ׂĂ����[����̂͂Ȃ��Ȃ�����ł�
�����ŁA����܂Ő��X�̐����֗��O�b�Y���J�����Ă���YAMAZAKI���ڂ�t�����̂�����@��̃f�b�h�X�y�[�X
�{�����Љ�鏤�i�́A�Ă������@�㕔�̃X�y�[�X��L�����p�������I�ȃc�[���ł�
�yYAMAZAKI/�R����Ɓz �����h���[�V�F���t �n���K�[�o�[�t�� tower �z���C�g 3605 �g����
������́AYAMAZAKI�̐l�C�V���[�Y�utower�v�̃����h���[�V�F���t�B
���p���ɂƂ��Ƃ�������d�l�ŁA���ʂɂȂ肪��������@��̃X�y�[�X���������L�����p�ł���X�O�����m�ł�
3�i�V�F���t�ɂ́A����p�i��^�I���Ȃǂ������Ղ���[�ł���̂ŁA���炩�肪���Ȑ��ʑ������X�b�L���ƕЕt����ł�

�V�F���t���������̂���X�`�[���ɁA�V�R�̃n���K�[�o�[��g�ݍ��킹�A�X�^�C���b�V���Ɖ����݂��Z�������f�U�C��
�������A�n���K�[�o�[�ɂ͐����ꎞ�I�Ɋ|���Ă������Ƃ��ł��A�ƂĂ��֗��ł��B
����ɁA�H�v����ł��낢��g�����t�b�N��8���t���Ă��܂��B
���x�̍����E�ߎ��ł��ς�����悤�A�K�␅�ɋ������̓h�����H���{���Ă���̂ł����������N���N�ł�
����@���肪�X�b�L���Еt�������h���[�V�F���t�A�F�l�̂��ƒ�ɂ��������ł���